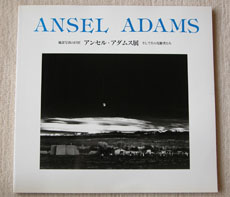|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2006.12.30. カミさんのティータイム:ダチョウの卵
ダチョウの卵を見た、そして食べた。人生お初である。
先日、トリ屋(といったって焼き鳥やの寄り合いではない)のちょっとした集まりに出席した。その宴席に、女獣医(じょじゅうい? なんかスゴイひびき)さんが差し入れてくださったものだ。TVなどで見てはいたが、やはりでかい。ニワトリ25から30個分というから、赤ん坊の頭くらいはある。 厨房から「うぉっ、うぉっ、こりゃー、割れねー」などと、格闘の雄たけびがとどろく。そうとう殻が頑丈らしい。しかる後、ふたつの大きなカニ玉となって登場した。ダチョウの卵のカニ玉である。味はふつうのニワトリの卵と変わりはない、と思う。黄身の色は山吹色かと想像していたが、家で食べているのより白っぽい。もっと野生的な味を期待していたたが、思いのほか淡白であった。少々、大味ってわけだ。 すっかり中身をぬかれたダチョウの卵を手に持ってみる。胴回り38.5センチ(因みにCDの外周が38センチぐらい。どうでもいいが、痩せ型の私の太ももを測ってみたら42センチ。)、高さ14センチほど、美しいクリーム色をしている。殻、あくまでもしっかりしていて、厚さ2ミリ、プラスチックかとおもわれるほど人工的だ。中の膜もすごい。サランラップを3枚くらい張り合わせたくらいにしっかりしている。これじゃ大変だ。これから生まれようとしている雛にはかなりハードだ。しかしきっと内側からの力には、弱くなっているのだろう。じゃないと、ダチョウは生まれずしてダウンだ。私は殻をやぶろうとしてへとへとになってしまった雛の気持になってみた。悲しくなってカニ玉への意欲がおちた。 ここで、知人のM氏よりダチョウ話のメールあり。アフリカでは「ダチョウの卵売り」というのがいて、少年が頭にのせて通過する車にセールスするのだそうな。“思わず買いたくなったと”メールにあったが、それは少年への愛か、単に卵への好奇心か・・・。しかし奥さんに叱責され思いはたせず、とあった。奥さんの気持、よーくわかる。旅先ででかい生卵買ってどうするっ! ダチョウといえば、オストリッチ、といえばバッグである。高級品の代名詞としてクロコダイルと並び称されている。幸いにしてどちらも持っていない。正直オストリッチのバッグのよさが分からない。あのブツブツがよろしいと思えないのだ。あそこから羽がはえて、まさに鳥肌なわけで、それを撫ぜてめでるのである。人は高価というだけで美しいと思えてしまうのだろうか。
2006.12.30. 気の長〜い夢
バード・フォト・アーカイブスも大晦日を迎えようとしている。モノクロ写真の収集、保存、活用、継承を目指して早くも2年半。切りなく思える仕事の山を追いかけ、生きる意欲がわいて尽きることがない。今年も精一杯だ。
これも、モノクロ写真やネガをご提供くださった方々をはじめ、多くの皆さまのお力添えあってのこと、感謝にたえません。この場を借りて、心からお礼申しあげます。 会社設立の時に、いずれ実現させようと決めた夢があった。提供された写真を活用して得られた純益を、野鳥や自然の保護活動に寄付させていただくこと。ささやかでも社会還元する意気込みである。それで自然が守られ、そのことをもって、無償でモノクロをご提供くださった方々へのお礼にかえさせていただきたいのである。それにはまず純益を出さねばならない。 バード・フォト・アーカイブスへのご寄付は、済みません、いくら高額でも寄付金控除の対象にならないのだが、それを承知でのご寄付は金額の多寡にかかわらずいつでも歓迎です。自然保護団体などへの寄付が実現の運びとなった際には、ホームページ上で寄付者のお名前を出させていただくので、几帳面に記録はとっている。  2006.11.22. カミさんのティータイム:鳥打帽
ヒューヒューと木枯らし吹く初冬のある日。
遅くに帰宅した夫は、両手で頭をなぜながら「ああ、寒っ」とつぶやいた。まったくだ・・・。おぐしがすっかり薄くなった後頭部はダイレクトに寒風にさらされ、ことのほか寒々しい。切ない。 「そうだ、この感じ、どっかで見たわ。ああ“北の国から”の、海辺の崖っぷちで風にあおられていたタコの干物のシーンのようだわね。(ひょっとして、イカだったかもしれない)」などと心のなかでつぶやいた。口にだしてはいけない・・・。 昔、円形脱毛症をわずらったことがあるので、毛髪の悲しみは少しは理解できる。胃のあたりから、ゆらゆらわきあがる寂しさは鼻を抜け、涙しそうだった。 と言う訳で、一気に帽子屋へむかった。本日のミッション「おやじの似合う帽子をゲットせよ」なのだ。 銀座トラヤは紳士ものの帽子が充実している。いわゆる銀座風のものから、おっちゃん風ニット帽、あぶない芸術家風ベレー帽まで充実している。そこで夫が心動かされたのは、“鳥打帽”つまりハンティング・キャップ。19世紀半ばイギリスの上流階級で狩猟用の帽子として生まれた。ときどき時代錯誤した銀座のおやじがパイプだの片手に、なにやら薀蓄(うんちく)をかたむける時に必要な小道具として使われるが、そんな恥ずかしい事はしてはいけないのよ。  そのチャコールグレーの鳥打帽は、店の棚に無造作に重ねられていた。しかしかなりの存在感。ラベルをみれば、“Borsalino”とある。イタリアのボルサリーノ社のものであった。例のイタリアマフィアがかぶるような中折れ帽は、スタイル名になってしまっているほどだ。あれは実は会社名なのだ。 2006.11.17. 「東京湾にガンがいた頃――鳥・ひと・干潟 どこへ――」 私の本ができた。身近な方々からのさっそくの反応を二、三紹介させていただく。 「大変ムードのある表装ですね。しかしはっきり言って売れる分野の本ではないですが、どうしても世の中に残しておきたい本ですね。」執筆を後押ししてくれた親友T君から。(う〜ん、同感。どっこい、密かに業界ベストテンの売れ行きを・・・) 「モノクロ写真の懐かしくも素敵な世界、そこから発せられるメッセージ…考えさせられることの多い本です。」一般書店販売に先立って、一早くFIELD ARTのホームページでPRしてくれたTさんご夫妻。(そう、「エピローグ」と「終わりに」の前半は、時間がなくとも読んでいただければ望外です。) 「鳥の本は山ほどあるけど、古き良き時代のバードウォッチングを伝える本はありそうでないよな。それに50年前のどうでもいい・・・どうでもいいとは言わないけど、捨てられていそうな写真がでてて、これがまたいいねぇ。」カメラ好きのベテランバードウォッチャーHさん。(まったく、なぜか捨てられずに残されていたモノクロ写真は、62点がデザイナーさんのコダワリですべて二色分解され、風味を増して本文を飾ってくれてます。) なんと言おうと言われようと、とにかく私には満足のいくできなのだ。お一人でも多くの方に読まれ、明日の環境を考えるきっかけとなり、それが自然を守る行動につながることを願っています。 単行本を著したことのない私はスタートでモタモタし、モノ静かで優しくみえる鬼エディターSさんにハッパをかけられること、しばしば。デザイナーのKさん・Tさんコンビに、この手のこととなると欠かせないカミさんとともにチームを組み、打ち合わせというか、一杯やって景気をつける方が主眼というか、そんなことを経て「オレが原稿書かないことにゃ何も始まらない」と理解した。 一心とはオソロシイ。見よ、ほぼ予定通り出版されたのだ。(塚本洋三記) 2006.10.21. カミさんのティータイム:パブロ・カザルス「鳥の歌」
秋の到来である。夏の暑さにやられた脳みそはナマコ状態を脱出し、その冷気を感じ引きしまりだした。ここ都心のど真ん中、いち早く秋の到来を感じるのは、悲しいかな自動販売機とコンビニだろう。缶コーヒーは“温か”モードにチェンジされ、コンビニの肉饅頭はガラスケースのなかで“ふくふく”と私を誘惑している。ああ、秋。
 チェロの天才パブロ・カザルスのライブ版を聴いている。1961年、時の大統領ケネディに招かれ、ホワイトハウスでの演奏会のものである。すでにもう何十回も聴いている。大天才バブロ・カザルスのチェロだ。故郷カタロニア地方の民謡「鳥の歌」。多くの人々が心ふるわせ、魂がゆさぶられたものだ。いろいろな書物や解説で、数々の賛辞がよせられ、私も幾度となくそういったものを読んでいる。感動しなくてはならない。 そういえば19の頃、おおいなる予備知識のもとに一曲の歌をきいた。ダミアの「暗い日曜日」。1933年ハンガリーで発売され、その後、販売・放送禁止になった。自殺するものが後を絶たなくなってしまったからだ。 2006.10.18. BIRDER誌連載が本になる
秋。雁、渡り来る。
初雁のメールが、というよりここは「初雁の便り」といきたいが、佐渡の鳥友から届く。 刈り取り後の稲田にいたマガン幼鳥2羽が飛び立ち、真野湾方向から飛来した18羽の本体に合流。鳴き交わしながら、カギになりサオになりして夕陽に輝く西空にシルエットとなって去り行く。収穫された黄金色の波、コンバインのエンジン音の軽やかな響き、稲わらの懐かしい香り・・・。 想像するだに、完璧な絵になるメール。初雁の便りをうらやむばかりである。   現在 鳥居から右に目を転じた現在の景観。1964年からの埋め立て工事で 昭和35年 千葉県宮内庁新浜猟場の沖。漁師がベカ舟を滑らせてくぐる鳥居の上を、ゴマ粒をまいたような50羽ほどのマガンが雲間を過ぎる。1960年3月13日 ▼
私は東京の下町は大川端にいて、ガンの渡りを気にすることもなくなっていた。
4,50年ほど昔なら、 「さぁ、もうそろそろマガンがやってくる頃だな」 気もそぞろに、私のホームグラウンドだった千葉県新浜へと向かう。まだ、2−300羽のマガンが定期的に渡ってきていた頃だ。 そんな昔、バードウォッチングにうつつを抜かしていた私の体験談が、来月初めには一冊にまとまって刊行される運びとなる。ずばり「東京湾にガンがいた頃――鳥・人・干潟 どこへ――」(文一総合出版)。
2006.9.29. カミさんのティータイム:若冲の鶏
若冲の描くニワトリは、闘鶏のように闘争本能むきだしだ。展覧会という文化的空間で、血圧があがってしまったかもしれない。気の小さい私にはこの絵は毒だ。しかし“尋常でない作品”はともかくよろしいとする癖(へき)にはぴったりなのだ。
「紫陽花双鶏図」のニワトリでも毒々しいほどに派手だ。オスのトサカなど炎のようにそそりたち、あご下の真っ赤なびらびらは、もったりと重そうにたれさがっている。目をこらしてみると、その顔は赤で塗りつぶされているのではなく、毛細血管がつながったように細密に描かれている。一見大らかなニワトリは、実は、羽の一本一本までパラノイア的に描かれた、細かな表現の集積であることに気づく。 ニワトリはリアルに描かれている風を装ってはいるが、じつはおおいに誇張されている。ニワトリはこんなポーズはとれない、ボデイの羽の固まりが不自然、紫陽花が大木のようだ、等々、ちいさなデフォルメのかたまりが、迫力のリアリティを生み出している。  2000年に京都で展覧会が行われ、若冲ブームがおこった。それまで私は、若冲なるもの知らなかった。しかし、その時期にテレビの番組に取り上げられたのであろう。絢爛豪華なニワトリの絵だけは知っていた。そして2006年、「プライスコレクション――若冲と江戸絵画」の大ブレークで、はじめて本物を見てきたのである。 ある時、TVの美術番組で知った。ニワトリと白いゾウが同じ作者であることを。かなりの驚きだった。しかし、どの作品にも若冲の個性は発揮されている。アタリ作品にもハズレ作品であってもだ。私たちに「まっ、いいか」と思わせるパワー、それが鬼才の真骨頂なのだろう。 この夏、あの衝撃のニワトリと白いゾウに、国立博物館で会えたのだ。 (塚本和江記)
2006.9.16. 急転直下でコンバーター
デジスコの道を選ぼうか、デジカメ一眼ならキャノン30Dにしようか。迷いはしばらくつづいた。ふと、浮き足だってヨドバシカメラへ走り、新発売のニコンD80を手にとってみたり。しかし猫に小判の感あり、いじけた。
結末は意外にあっさりついた。 手持ちのコンパクトデジカメ、ニコンクールピックス5700に、別の用事でシャッターレリーズが使えるものか、使えそうにもないなとか思いつつマニュアルを繰っていた時だった。ふと、目に飛び込んだ字が“コンバーターレンズ”。 こんなものがあったのだ。私が手におえるのは、これだな。 さっそくヨドバシへ。ああ、せっかく良さげに思えたコンバーターは、製造元でも品切れと知らされた。ネットでていねいに探せばみつかるかもとは、店員の話。ネットでまともに目的を達することのない私は、いきづまった。 帰宅して、“押しかけ弟子”の私が、“隠れ師匠”の写友にメールでことの顛末をボヤいた。デジカメのスゴ腕で、じっくり構えて鳥心をねらう撮影姿勢に共感させられる関西のMさん、すばらしい画像を時々送ってくれて私を唸らせるMさんからは、かゆいところに手のとどくような情報が、即刻返ってきた。さすがのPCオンチの私でも、そのとおりにやってネットですぐさま希望のコンバーターがみつかり、購入を即決。 数日後ケンコーのコンバーターとアダプターが届けられた。高級デジカメのレンズとは、見た目に、そして持った手に、カル〜イ感じは否めない。しかし、x1.7倍だ。生涯300mmレンズまでしか持ったことのない私には、野鳥撮影の“武器”になるに違いない。年甲斐もなくウキウキする。レンズの味がどうのとかウルサイことは言うまい。気づかいない機材とのつきあいの方が気楽でよろしい、と自分を納得させたものだ。  手に入れて1週間ほど、撮るものもなくコンバーターは机の片隅で所在なげだった。 2006.8.17. カミさんのティータイム:ゆでたまご & むきたまご 八月である。こちら北半球は夏まっさかり。去年より暑さはマシ、というものの思考力ゼロの日がつづく。アルコールがだめな私はビールで暑気払いもできず、ひたすらぐずぐず言いながら時を過ごす。 以前TV番組で、六本木の男性ダンサーのドキュメントをやっていた。狭い舞台で鍛えぬかれた肉体が踊っている。かぎりなくヌードにちかい。ダンスもボディもかなり、すごい。技術においても、セクシーさにおいても圧巻である。興奮した女性たちは、お気に入りのダンサーに、太ももとパンツの間に紙幣をはさんでいた。洋風おひねりというわけだ。  最近はAV全盛のおかげで、ポルノ映画館は斜陽の一途をたどっているらしい。しかし昔はどこの町にも、一軒くらいはピンク映画館がたたずんでいた。ひっそりと。そしてたいがい、ソレは名画座のそばにあったものだ。私が足繁くかよった名画座しかり。前を通るたびに、うつむいたまま黒目だけををきょろきょろさせ、すばやく看板をチェクするのであった。 2006.8.8. デジスコに挑戦
私ではない。
私がデジスコに走らない理由は、機材調達に遅れをとったほかにもある。デジスコでとれた写真のおおくのものが、一見して「ウワッ!」とは驚く。だが、明日があるのに今を別れがたい恋人にみつめられているような、心奪われるほどの雰囲気のある画像になかなか出会えないからだ。 確かに、あのドアップ、いや、ド・ドアップには、参る。くわえて、ピントのよさなんて、気持ち悪くなるほど。なるほど、デジスコは革新的だ。野鳥写真の新ジャンルが拓けたにはちがいない。 現段階では、撮る側も鑑賞する側にも、デジスコならではの写真が撮れること自体に深く興味がひかれ、それで満足しているのではないだろうか。いつまでも、部分拡大のような単なるドアップの鳥では、飽きがこようというもの。できのよいカービングの鳥を撮ったような画像で気をゆるしていてはいけないのでは。写真図鑑むきのような画像だけでは、もったいない。一枚の作品として見ごたえのある内容を期待したいものである。 デジスコファンの皆さん、勝手を申してごめんなさい。平にご容赦を。 一方、よりよい画質で撮れる光学機材の開発が、メーカーさんの努力ですすんでいくにちがいない。デジスコ写真文化が着実に成熟していってほしいものだ。 自ら試みもしないで、デジスコ写真が気にいらないもヘチマもないものだ、とは感じている。白状すれば、「デジスコで野鳥撮影が楽しめる本」(文一総合出版、2006)を手にいれたり、デジスコ経験もないのにデジスコクラブに入会したりもしている。 心がゆれてきているのだ。乗りおくれたバスを追っかけようか・・・。  と思っていたら、カミさんがメモ帖代わりにと、手のひらサイズの薄型デジカメ、カシオエクシリムEX-S600を購入した。レンズ口径は指の先ほど。これなら我が最旧式初代プロミナーの接眼部口径と大差はない。冗談半分、カミさんに、「デジスコしてみたら?」 プロミナーにセイタカシギを入れて促した。千葉県の谷津干潟自然観察センターから見える、通称「お立ち台」の上で3卵を抱卵中のセイタカシギだった。私には、半世紀もお世話になっている愛用の初代プロミナーで、なにが撮れるか試してみたかった、下心あり。 完璧に浮き足立った。気を取り直してちょっとデジカメに挑戦しようか、とマジ思ったことは確かである。 (塚本洋三記)
2006.7.15. カミさんのティータイム:「たまご」
ある日、野の果てに忽然と現れた巨大な卵。 
気をつけて欲しい。たいていの人たちの「絵本」という概念でページをめくると、それはおおいにはぐらかされる。いや、横っ面をはりたおされる。絵本というよりストーリーのあるデッサン集といったほうが、より近いだろう。言葉は一切ない。木炭で描かれた線は黒々と激しい。大胆で力強い絵、メッセージ色の強いストーリー、ありていに言えば「とても女と思えない・・・」。
ページを開く。度肝ぬかれた。すでにこの作家のものをいくつも目にしているのに。いや、いままでの作品を知っているからこそ、よけいに息をのむ。絵本コーナーにあるのに、「たまご」は甘くない。毒だらけである。人間の愚かさを揶揄しているのか、人類が何者かにのっとられるか。本の中のたまごは、まるでエイリアンのたまごのようだ。あるいはこのたまご、核弾頭にもみえる。おそろしい話である。 この言葉なきストーリーどう読むか? 結論は読者ひとり一人にゆだねられている。であるからして、自分の知能レベルを試されているようで、ますますおっかない。そういう訳で、あまり多くを語りたくない・・・。
絵本作家としての彼女の作品は、せつなく優しく、静謐である。私はその絵本の世界を愛している。クマのおじさんとネズミの女の子の、胸がキュンキュンなりそうなシリーズなんか、こっぱずかしくて言いたくないほど好きである。「あのネズミの女の子のように、完全無欠に、まるごと愛につつまれたなら、ああステキ」などと、いい年してかなり不気味な空想をし、夢見るオバサンのひと時に酔う。
二面性をもつ彼女は、絵本作家としてはガブリエルの名前をつかい、「たまご」や「アンジュール」等のアート系の作品は本名で発表している。(日本はすべてガブリエル・バンサンの名前で出版している)彼女のシリアスな世界と、優しく繊細な世界、どちらも魅力的である。 
2006.7.7. 最旧式プロミナーでデジスコ?
1957年。バードウォッチングの神器として登場したコーワのPROMINARに、私が最初に出会った年だ。「うお、これは・・・」20倍なのに、野鳥識別に威力を発揮し、その性能にタマゲタものだ。なにぶん高価なもので、数少ない持てる仲間のこのレアモノを覗かせてもらったものだ。
1978年。アメリカから帰国しての探鳥会。堤防にズラーッと砲列の“プロミナー群”。この様変わり。カルチャーショックだった。 “望遠鏡”と呼ばれる代わりに、一時は“プロミナー”と通称されていたが、追っかけ、他社の製品が出揃ってきた。どこ製であろうと、「あっ、あの鳥、プロミナーにいれてみて!」と叫んでしまうのは、台頭プロミナー世代の私。 望遠鏡(フィールドスコープ;スポッティングスコープ)があれば、確かに心強いバードウォッチングの友ではある。それが、時経ずして、バードウォッチングの必携品のようになってしまった。ああ、「バードウォッチャー1人にスコープ1台」時代の到来である。 1990年代中ごろ、写真撮影にも異変が起きた。伝統的なカメラに代わるデジタルカメラの登場である。コンパクトデジカメは、カメラのメカ音痴にでも簡便この上なく扱える。とにかく撮れる。というか、撮れてしまう。すべてオート設定のデジカメ任せ、ONにして被写体を定め、シャッターを押すだけである。手振れ、ピンボケ、露出不足、二重撮り、フィルム交換・・・そんな単語知ってるだけで笑われてしまうぜぃ、いずれも死語同然だ。しかもデジカメなら、瞬時に結果が確認できる有難さ。便利さには勝てない。あっさり、銀塩フィルムのカメラを凌駕した。 21世紀へと移るころ、そのコンパクトデジカメをフィールドスコープと合体させた超望遠効果の野鳥撮影方法が試行錯誤され始めた。誰が予想しえただろう、あっという間にデジスコ時代の夜明けを迎えたことを。 
本当にビックリさせられる。なんとも容易に誰でもが野鳥の撮影を楽しめるのだ。野鳥写真の新たな時代がやってきた♪
フィルムカメラ世代の私には、わかっちゃいるが未だにどこか納得しにくい、デジスコ文化。第一、やすやすと野鳥を撮られては、私しゃ、やってられないのだ。簡単に楽しく撮れてどこが悪い。心の整理がつかないそばから、デジスコ画像をみせつけられる。やり場のないクヤシサ。 私は、メカ的にも気分的にも完全に乗り遅れた。 いや、デジスコのデジ部分は、なんとか1台、ニコンのクールピクス5700を予期せず手に入れた。記録写真に便利に使っている。それが9700だったならデジスコ向きなのに、と知らされたときは、かなり後の祭り・・・。 かくして、デジスコには縁がありそうでないあたりに、私は存在している。 (塚本洋三記)
2006.6.25. カミさんのティータイム:鳥越まつり
「火事とけんかは江戸の華」というけれど、もうひとつ忘れちゃならねぇものがある。まつり、そう、江戸の祭り。  こんなに狭いところに有名どころの祭りがひしめけば、血の気の多い江戸っ子、いやがおうにも競争心は燃える。となりの浅草三社まつりに負けちゃならねえ。と言う訳で、ここ鳥越神社は巨大なみこしをつくった。あっちのみこしが三基なら、こっちは一つでどでかいのを。千貫御輿(せんがんみこし)である。一貫は3.75kg、つまり3750kg。これが御輿として重いのか軽いのか、はたまた、ウソかホントか想像の域を脱しないが、実際目にすると、ともかくでかい。 若かりし頃、三社のみこしを担いだことがある。みこしの魅力が少しばかり分かったような気がした。コレはワイワイと人と群れる喜びではない、と直感した。「せや、せやっ」と掛け声をかけながら、自分の中に入っていく。どんどんはいっていく。魂の内へ、内へ。そして恍惚。 祭りといえば、縁日ははずせない。毎年似たような出店ばかりなのだが、なんだかやっぱり、行かねばならぬのだ。子供の頃から、近所の寂しい縁日ですら行きたかった。雨の中、たった一人で金魚すくいをするようなガキだった。まずは神社うらの飴細工屋をひやかし、やっぱり精密さに感心する。とうもろこしを買い食いし、金魚すくいの店をのぞく。うなぎ釣りもあるし、ミドリガメすくいもある。 備考:鳥越と浅草のみこし争いは、ご近所の伝承である。神社さんにウラをとってはいないので、そのへん、一つよろしく。 すべからく玉子料理は好き。甘いのも辛いのも、洋の東西を問わずなんでもウェルカムである。思う存分いただきたいのだが、コルステロール値が高いのでそれなりに気にしながら食べている。  この玉子かけご飯、ちかごろ巷で静かなブームになっていることをご存知だろうか。なんたって玉子かけご飯用の醤油が発売されているぐらいだ。その味をためすべく、私はデパ地下へと走った。 外人さんは玉子かけご飯は食べられるのだろうか。聞く話によると、生玉子はいかんらしい。すき焼きはGOODだが、生卵をからめて食べるのはNO GOOD なのだそうだ。もっとも時代は進んでいる。ニューヨークの片隅で、マッチョめざして生玉子を一パックほどペロリと飲んでいる奴が、ざらざらいそうな気もするが。 2006.5.24. カミさんのティータイム:玉子かけご飯
2006.6.17 「歩く男」
誰しも心に残る写真がある。あれもそうだったのか・・・。私の記憶にある何枚かのモノクロ作品が、アンリ カルティエ=ブレッソン(1908-2004)のものと分ったのは最近のこと。 なんと、そのカルティエ=ブレッソンが、かのジャコメッティを撮っていたのだ。 アルベルト ジャコメッティ(1901-1966)、偉大なる芸術家。生涯のテーマは、「見えるものを見えるままに表わす」こと。無学にもそんなことを、先日ジャコメッティの企画展を観にいって私は初めて知ったのであるが。 カルティエ=ブレッソンが撮ったジャコメッティの写真の中でも、私を魅了した一枚とは―― 
カルティエ=ブレッソン vs. 「歩く男」
写真は1961年の作である。果たしてカルティエ=ブレッソンは、ジャコメッティの素描画「歩く男」を意識していたものかどうか?
素描画は、ジャコメッティのジャコメッティたる“歩く”ブロンズ像のいくつもの作品の原点かとみなされている。その素描画こそ、企画展で私を釘づけにしたものなのだ。ナナフシ(やせっぽちな、脚も体も針金のような昆虫)を立てに置いたような、よく見れば右に人が歩いているような、リトクレヨンで描かれた「歩く男」。それは、制作年不詳とある。 考えるに、カルティエ=ブレッソンは、ジャコメッティ本人とそのジャコメッティが創ったブロンズ像を同じ重みの被写体として捉え、存在の本質をそれぞれの被写体で追求し、かつ関連づけてみる。そして「“見えないもの”を見えるままに」レンズを通して印画紙に創出してみよう。そんなカルティエ=ブレッソンなりの深遠な意図があったのではないだろうか。 存在そのものを「見えないもの」と捉えるか、「見えるもの」ととるか。本質への根源的な視点は、カルティエ=ブレッソンとジャコメッティでは異なるように私には思える。真摯な探究は二人の共通点だ。では、「見えないもの」あるいは「見えるもの」を「見えるままに表わす」とは? この不到達の命題に、カルティエ=ブレッソンは、同じ芸術でも彫刻に代わる写真を手段として勝負する無言の挑戦状をジャコメッティに突きつけたのではないのか。 さらに推測を遊ばせれば、その写真作品をジャコメッティに示し、「どうだっ」と言いたかったかどうかは別にして、ジャコメッティの生涯のテーマ「見えるものを見えるままに表わす」の達成度をジャコメッティ自身が確認できるよう、その手段を写真が担えることを示唆する含みがカルティエ=ブレッソンにあったのではあるまいか。 「歩く男」絡みの、巨匠と巨匠の洞察が激しく交錯する作品中の作品。一枚のデッサンと、それを意識して構図したに違いない一枚のモノクロ写真に思いを致して、私は言い知れぬ緊張感にしびれたのだった。 なにごとによらず、ホンモノに接するは至福だ。私は心地よい興奮を覚え、神奈川県立近代美術館を出た。中空に、東京都内ではすっかり見られなくなったトビが1羽、ゆっくりと輪を描く。その軌跡を凝視して、なにか哲学しなければいけないような気分だった。 2006.5.20. ちょっとピンボケな話 モノクロ写真が全盛であったころのカメラ機材では、ピンボケ写真がよく撮れた。親父自慢のローライフレックス4x4を持ち出してみても、たしかにファインダーはうす暗い。ピントをあわせること自体が大変であった。付属のルーペで、まあ、ここいらでピンがきてるかな、などと思い、ままよとシャッターを押す。押せばオートでピントがあってしまう今のデジタルカメラとは、ワケが違う。ウデと経験を磨くほかなかった。 
撮影(というのもおこがましいが)◆塚本洋三
1953年5月31日 私の鳥ネガ第1号:コサメビタキの巣 静岡県須走
富士山麓須走探鳥会の常宿、米山館の庭で、
コサメビタキの巣を教わる。 野鳥をファインダーで覗く初体験。胸が高鳴った。 頭のなかには、親鳥が抱卵する傑作写真ができていた。 1週間ほどして現像があがってみたら、 親鳥? どこに?(矢印の先らしい)。 実にこんなハズではなかったのだ。 引伸ばせばなんとかなるものかと、 赤でトリミング指定の跡もいじらしいブローニー版のベタ焼き。 それが半世紀を経て見つかった。 ネガケースに「シャッター50分の1、絞りF5.6、距離8フィート、薄曇」の鉛筆書き。 カメラは、確かスプリングカメラと記憶している。 標準カメラで野鳥を撮ろうと、 無謀な努力を繰り返していた、あのころ。 中学生の夢が、よぎる。 標準カメラで撮れるネガ上の鳥は、どれもが小さい。小さ過ぎる。それならばと伸ばして大きくすると、ボケてくる。種類が判りようもないほど、文字通りボケボケの鳥影でしかない。そんな写真が増えた。それでも私には、野鳥を撮ったのだ!との新鮮な思い。これは歴史だ。 Tさんまでとは言わないまでも、できるだけピントがあって、少しでも大きく撮る、というのが私にはとても難儀(技)だった。ところが、ある日、鬼の首をとったのだ。ピントのよい写真、必ずしも傑作ならず、と。Tさんのことを言っているわけではない。ピンの甘い写真が即凡作とは限らない、と気づいたのである。ピントを超越した「写真の味」が醸し出されている写真こそ、写真らしい写真ではないか。
Tさんが遠路訪ねてきてくれた。挨拶もそこそこにビールがつがれるや、二人の出会いの話を持ち出してきた。私は忘れていた。もう40余年前のこと。野鳥業界で互いを知っていながら、ゆっくり飲んで語るのは、実は初めてである。
自分はビジュアル人間だから、という。心で見たことは覚えている。聞いたこと、言われたことは、右から左だそうだ。それが奥さんのひんしゅくを買う所以とか。結婚記念日だけはご自身の誕生日と同じなので、忘れようがない。コト無きを得ている。 噂にとどろく呑み手のTさん。ご本人に言わせると、酒を飲む間も頭の中は考えている、書くべき本の構想も練っている、と。毎晩飲んで考えたなら、定年退職後の今日までに本の1-2冊は書けているハズだ。奥さんの採点は、こと呑み助Tさんに関しては、すこぶる辛い。 最後は私お薦めのジン、BEEFEATERの登場である。松ヤニみたいな匂いをうけつけない人もいるからムリしないでと、言ってるそばから一口。 
2006.4.18. カミさんのティータイム:ひよ子
生きものの形をした菓子を食べる時、たいていの人は一瞬躊躇し、軽く悩む。「さて頭からパクリといくか、尻からにするか」。私の場合は頭からいく。形あるものは頭からいかねばならない、それが正しい食べ方と信ずる。 先日“ひよ子”を食べた。そのとき、久ぶりにそのお姿をじっとみつめた。記憶にある“ひよ子”よりずっと「カワイイ」(癪だが、便利な言葉だ)。丸くて、ほっこりしている。愛らしい。見る角度をかえると、寸づまりのオットセイに見えなくもないが、顔に鼻のような嘴がついているので、やっぱり哺乳類ではない。カワイイねー、といいながら、二口でいただいた。 この手の、生きもの具象菓子を口にするとき、人は欲望と謝罪の気持の中でその腹におさめる。「ゴメン、だけど、美味い」などとつぶやきながら。そしてどこかでうごめくサディスティックな感情を認め、いたいけな小動物を食ってやるのだ。それは弱肉強食という生物に普遍の論理を、我々に想起させているのではないだろうか。 
2006.4.1. タイガの雫 (しずく)
2006.3.24. カミさんのティータイム:「鷺娘」礼賛

坂東玉三郎の「鷺娘」を観てきた。
真白き鷺の化身が、傘の中に佇む。恋に身をやつした鷺娘は、次に町むすめに変化し、最後にまた鷺の化身となって、雪のふりしきる中、悶絶し地獄の苦しみのうちに、息たえる。 江戸時代には、恋に執着すると死後地獄の責め苦にあうという思想があったという。今に生きる私には、恋をしたくらいで、なぜそんな目にあわされるのかさっぱり理解できないが、ともかく羽をふるわせながら、鷺娘は逝ってしまうのだ。 この舞踊作品は、いわば日本の美意識のかたまりのようなものである。人界を越えた美しき者が薄夕闇のなか、果てる。やはり日本人の美学は、死によって完結されるのか。 隅からすみまで日本的、ぬかりはない。わかっているが、すっかり情緒にやられてしまう。嗚呼、せつない! 玉三郎は、壮大な美のオーラを持つ芸術家と拝察している。玉三郎の美しさは、あきらかに他と種類が違っている。すばらしい芸をもった歌舞伎役者や、卓越した技術をもつ舞踏家はたくさんいらっしゃる。しかし彼の場合、美しさの位置が尋常ではないのだ。あの世とこの世の間に存在しているのだ。その危うい位置は、技術とは別次元の、つまり訓練ではどうにもならぬ類である。まさに美の天才なのだ。嗚呼、なんと崇高な! なぜサギなのだろう。日本で美しい鳥といえば、まずタンチョウであろうに。しかしサギなのだ。江戸時代は両者とも身近に見られたという。どちらをえらんでもよい訳なのだが、ツル娘とはならなかった。 鷺娘といっても、美しくないサギでは困る。美しいから切ないのだ。子供のころから日本舞踊をならっていたので、そこそこ舞踊は観ている。この繊細な作品も、どうしようもない踊り手が演じると、とんでもないことになる。サギにあらず、白色レグホンが今まさに絞められ、断末魔の苦しみでのたうっているかのごとき有様となる。「ったく騒々しいヤツだなぁ」と腹の中でつぶやく。 玉三郎はニューヨーク、ロンドンでも大絶賛と聞く。さて、アングロサクソンにこの美しさが理解できるのかと毒づいてみたりもするが、実はかなり嬉しい。
|
|||||||
| Copyright, 2005- Bird Photo Archives All Rights Reserved. |